
一人ぼっちで、帰り道すら分からず
ひとりぼっちで、転がる石のように
真冬のN.Y.にたどり着いて歴史を変える瞬間までを、ティモシー・シャラメがディランになりきって演じた映画。コロナ禍で5年間準備をかけた以上に、本人が奏でる歌もギターも驚くべき響きを持っていた。どこまでが史実でどこまでがフィクションなのかと思いつつ観始めたが、次第にそんなことはどうでもよくなる程引き込まれてしまった。ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロの柔和な雰囲気もとてもよく、「風に吹かれて」を聴かされて思わず横でハーモニーをつけるシーンが印象的だった。ギターのベースラインが下がっていくのにメロディーも下降していくところも新鮮な驚きだった。
実は「ユダ(裏切り者)」というヤジは、66年のロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでコンサートでの出来事。映画の中ではニューポート・フォーク・フェスティバルとして描かれているが、映画の流れでは違和感がないように感じた。「Like A Rolling Stone」の録音シーンはスタジオ内擬似体験しているようで思わず身を乗り出してしまった程だ。
健太さんの「ボブ・ディランは何を歌ってきたのか」を予習のために関連部分だけ読むつもりが最後まで読んでしまい、映画の後には「No Direction Home」のVTRを一気に観てしまい、北中さんの「ボブ・ディラン」も読みはじている。映画はディランの音楽生活の一部だけを取り上げているけど、今でも驚きを与えてくれるディランの新作が待ち遠しく思えてならない。
映画のタイトルはオリジナルのままの方が良かったかと。映画もVTRのタイトルも、「Like A Rolling Stone」のサビから引用されているのだから。


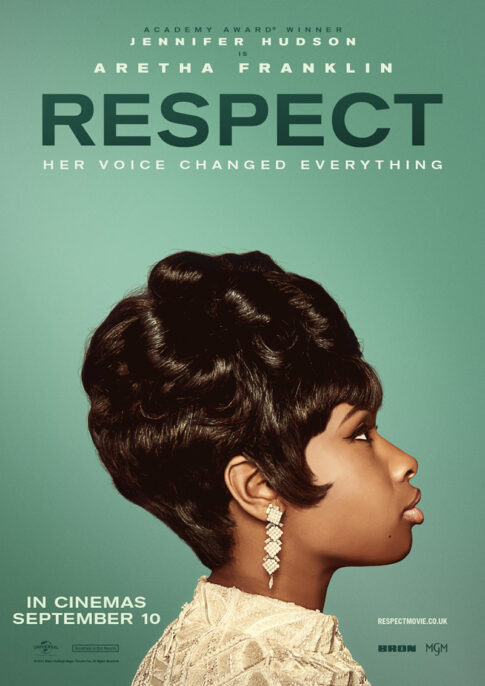


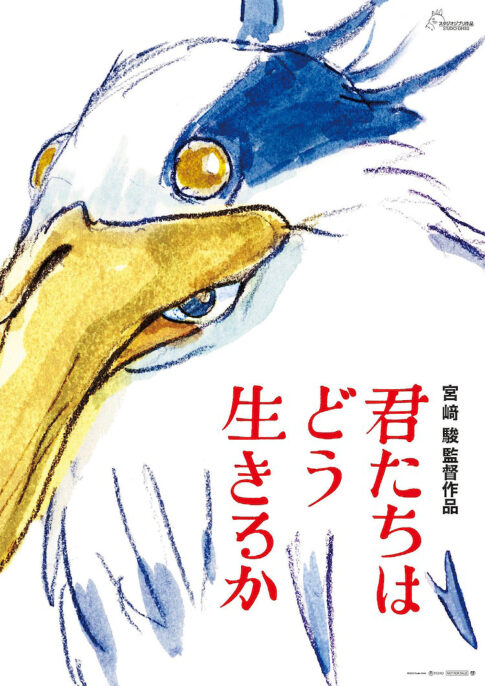
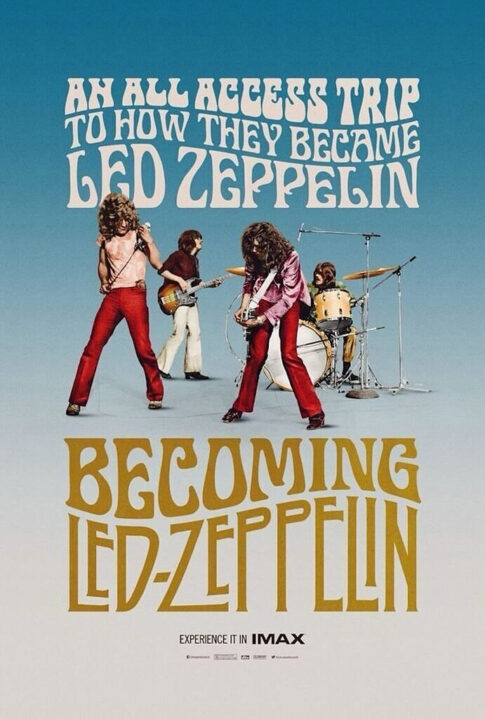

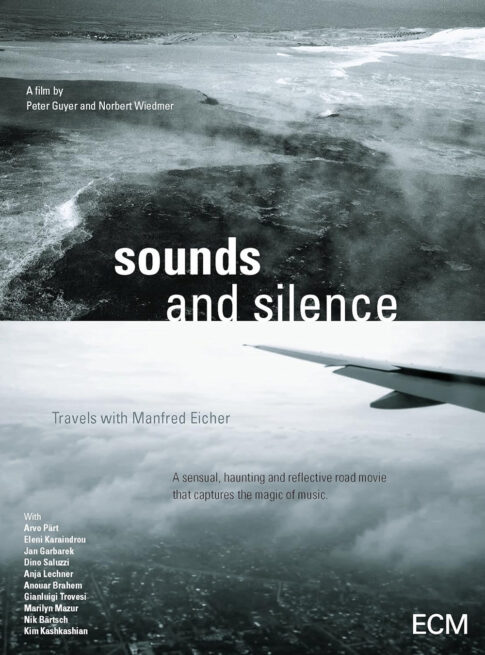
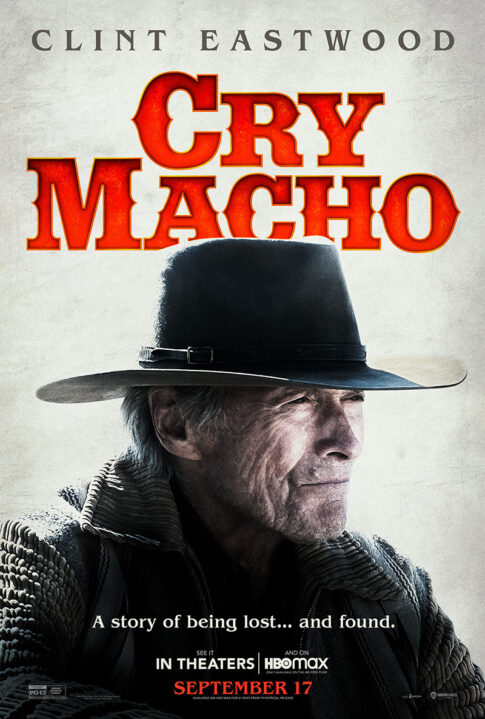
コメントを残す